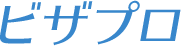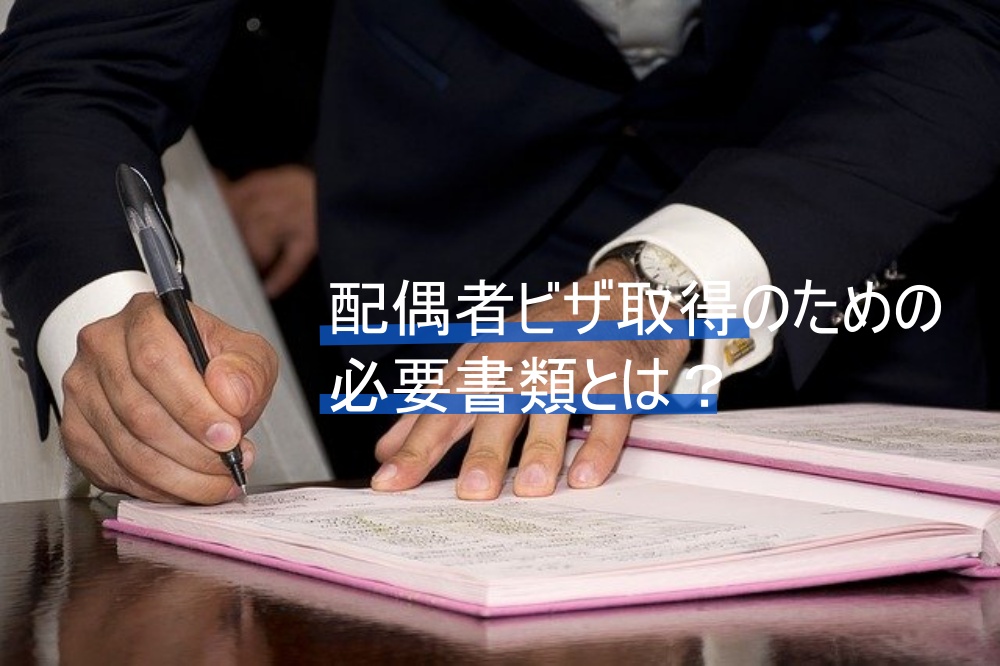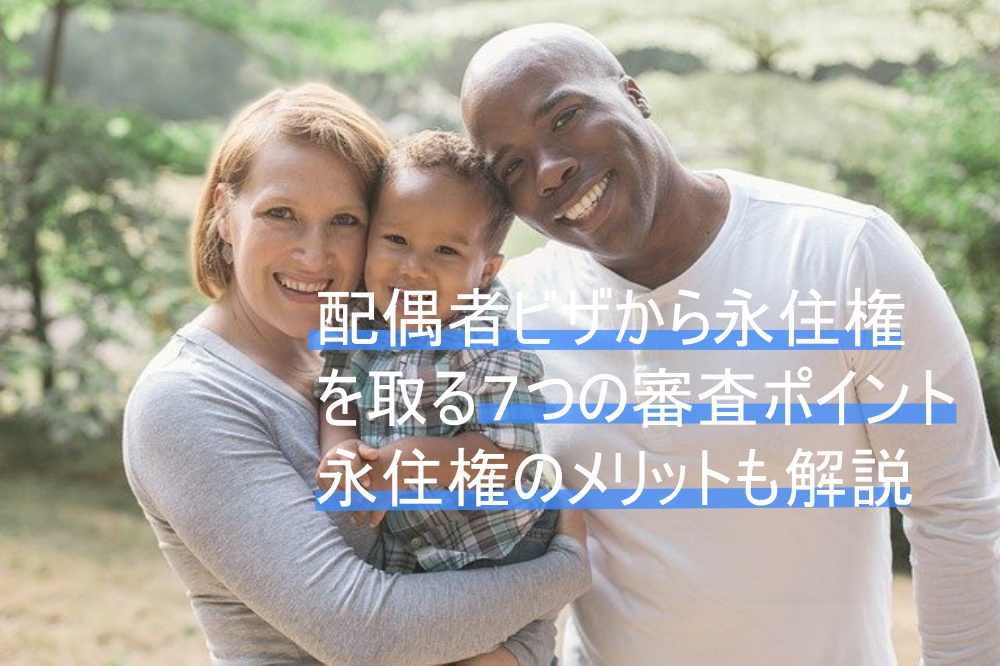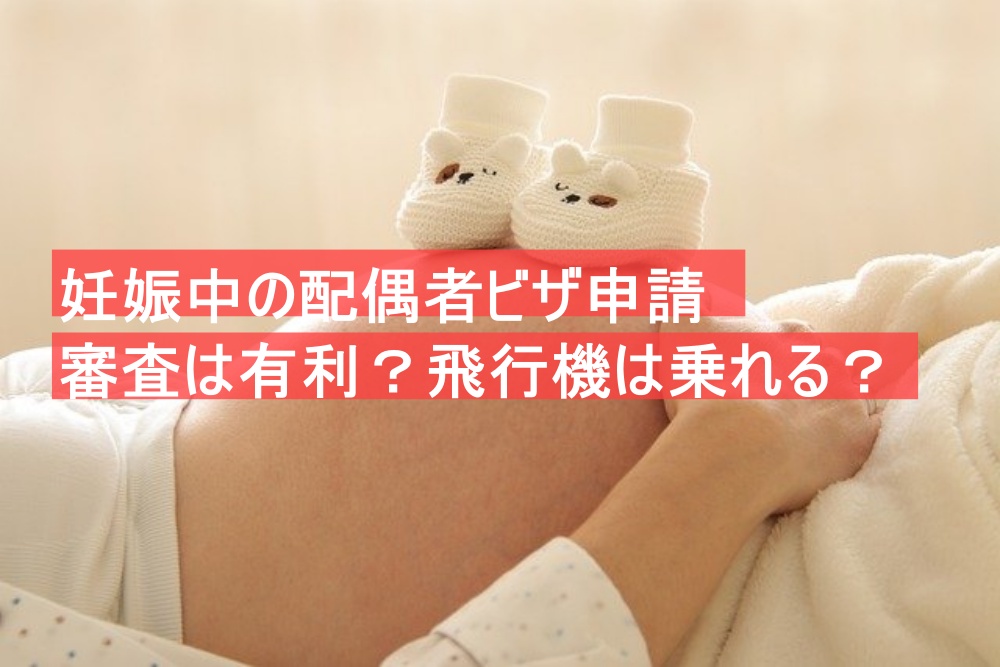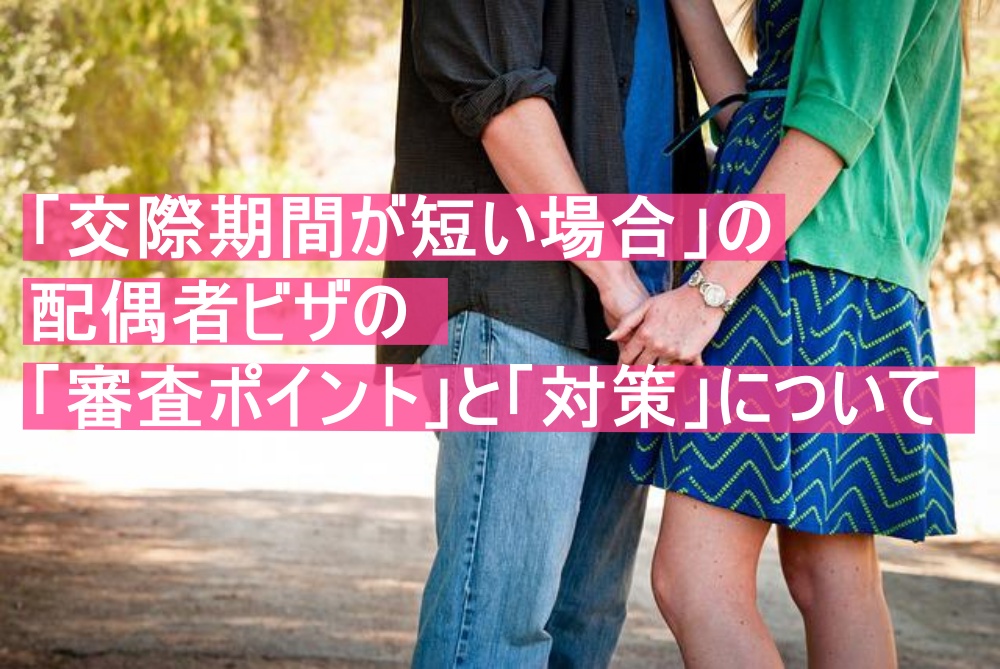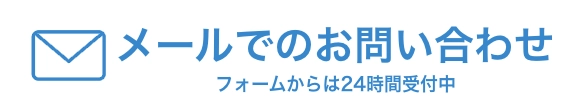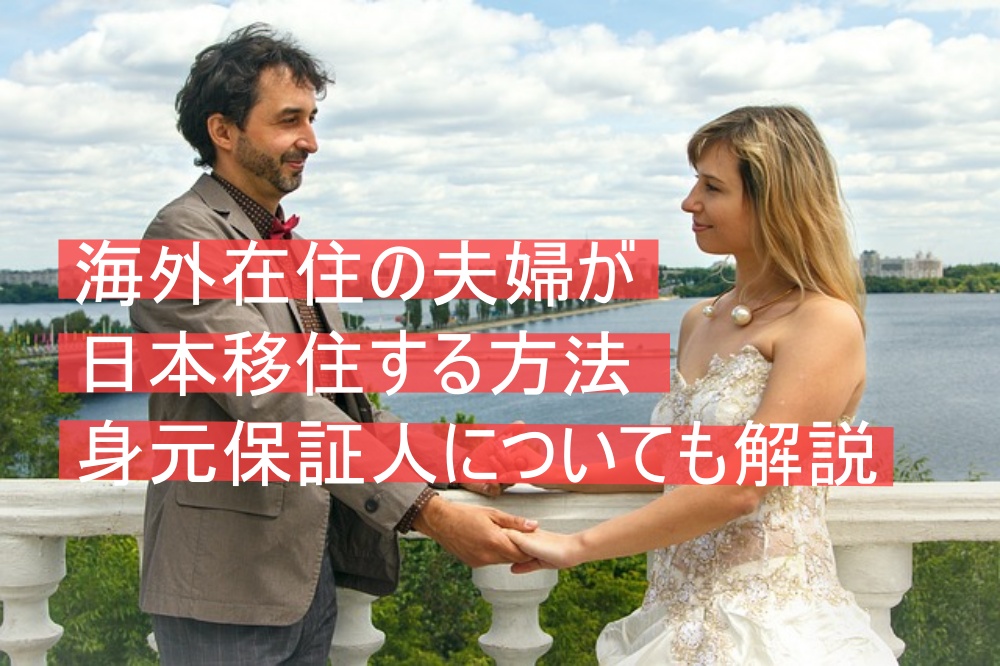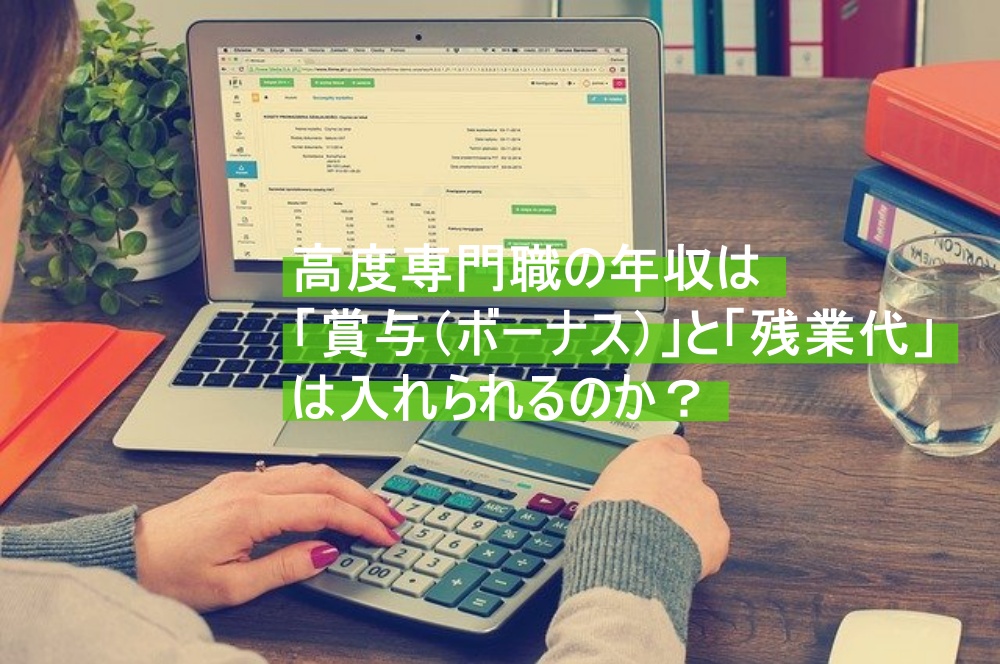配偶者ビザで入管から追加書類(資料提出通知書)を求められたときの対応方法
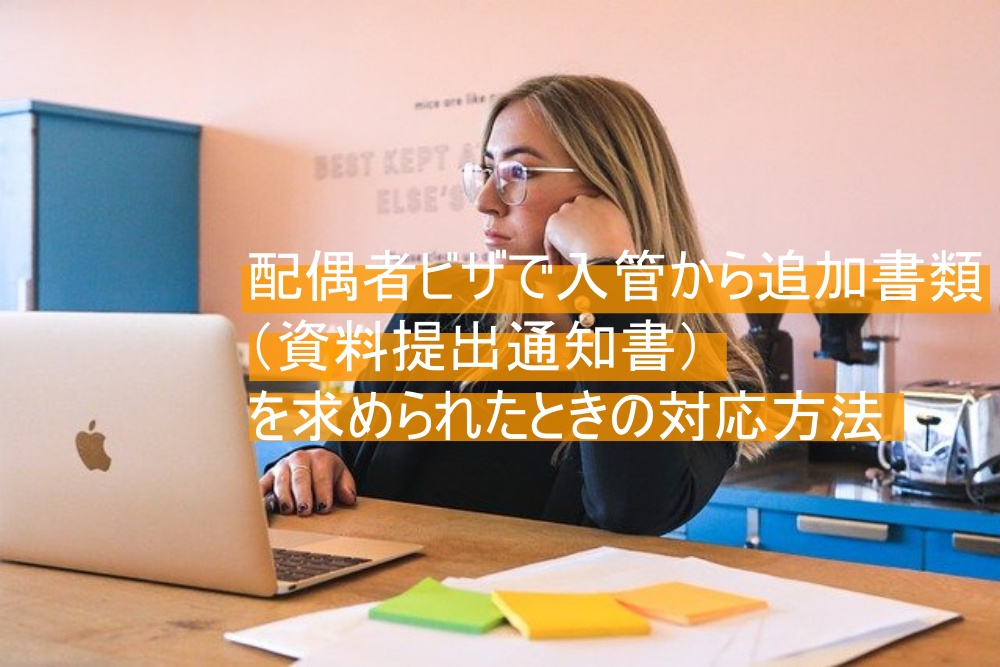
配偶者ビザの申請において、申請後に入管から追加書類(資料提出通知書)を求められる場合があります。
追加書類が求められる場合は、何かしら入管から疑いをもたれている場合があります。
追加書類の提出には期限も決められているため、早く確実に入管の求める書類を提出すれば十分に許可される可能性は残されています。
今回は追加書類を求められた際の対応方法につい一緒に見ていきましょう。
目次
資料提出通知書とは?
「資料提出通知書」は、入管の審査の中で審査官が不明点や不審点があった際に、追加で書類を求める際に送られてくる書類のことを言います。
具体的にどういった場合に、追加書類を求められることが多いのでしょうか。
追加書類(資料提出通知書)が届くケース
- 資料が不足している場合
- 審査の中でより詳細な書類で確認したい事項が出てきた場合
- 疑いあるところがあり、明確にするために書類を求める場合
何もやましい事がなくても資料提出通知書が送られてくると,「不許可になるのではないか」「どのように書類を準備したらいいのかわからない」「求められた説明文をうまく作成できない」など,混乱してしまう方も少なくありません。
入管のHPに記載されている必要書類だけでは不十分なことが多い
「ちゃんと必要書類を提出したのに何で追加書類が必要なの?」と思われる方もいるかもしれません。
仮に入管のHPに記載されている必要書類をすべて提出したとしても、追加書類を求められることが多くあります。
理由としては、入管のHPに記載されている必要書類は、「最低限必要な書類」のみを記載しているだけになります。
そのため配偶者ビザの審査において、「結婚の信ぴょう性」や「安定した収入が確保できているか」などの審査項目に対して、より詳細な資料を求められることになります。
入管の審査のスキームについて
入管での配偶者ビザの審査では、次の4つに振り分けられて審査が進んでいきます。
配偶者ビザでの審査スキーム
- 許可が相当な配偶者ビザ案件
- 慎重な審査を必要な配偶者ビザ案件
- 明らかに不許可に該当する配偶者ビザ案件
- 追加で資料を求める必要がある配偶者ビザ案件
追加書類が求められる場合は、④に該当します。
④は追加書類の内容によって、「許可になるか」「不許可になるか」審査結果に大きな影響を与える局面となっています。
追加書類の対応の仕方
それでは、追加書類(資料提出通知書)が届いた場合、どのように対応していくべきなのでしょうか。
資料提出通知書で求められる追加資料は、配偶者ビザ申請の許可・不許可を決めるとても重要な資料となります。
そのため,入管からの追加資料・説明文の提出に対して、無視をしたり,適当に回答してしまうと不許可のリスクが非常に高まってしまいます。
最初に確認するべきは、「役所等で取得する書類なのか?」「文章を作成して説明しないといけない書類なのか?」です。
求められている追加書類の種類はどれか?
- 役所等で取得できる書類か?
- 会社等で取得できる書類か?
- 何か文章で説明しないといけない内容か?
役所等で取得できる書類の場合
追加種類が、役所で取得するだけのものであれば難しくはないです。
入管の意図も汲み取りやすいかとおもいますので、指示された書類を取得してください。
なお注意する点としては、「住民税の課税証明書と納税証明書」を求められた場合です。
住民税の課税証明書と納税証明書を求められた場合の注意点
- 納税証明書に未納額がないか確認する
- 課税証明書の総収入額が少なくないか確認する
- 非課税証明書または書類が取得できない場合
未納額がある場合
万が一、納税証明書に未納額がある場合は、未納額を支払い未納がなくなったものを再取得して提出するようにしてください。
未納額が多くて一度に納付できない場合には、役所と相談して分割で納付する手順を決めてください。
分割での支払いになった場合は、入管に納税証明書の提出をするだけでなく、分割になっている旨を説明して、なぜそうなってしまったのかも含めて、理由書を作成してください。
※納期未到来の未納額は残っていても問題はありません。
課税証明書の総収入額が少ない場合
総収入額が少ない場合には、収入の安定性がないと判断されてしまう場合があります。
この場合も課税証明書を提出するだけではなく、過去の状況を説明する理由書を作成し、今後の生計維持プランを入管に説明するようにしてください。
非課税証明書または書類が取得できない場合
「過去の収入が少ない」または「海外等に住んでいるなどの理由で住民税の課税証明書と納税証明書が取得できない」場合は、その理由を説明する文章を作成してください。
生活の安定性という意味では過去の収入額は重要なポイントですが、配偶者ビザ取得後の生活をどのように送るのかの方が大切になりますので、理由書の作成次第で十分に許可の可能性はあります。
会社等で取得できる書類の場合
「在職証明書」や「雇用契約書」「給与明細のコピー」など会社で準備できる書類を求められた際には、入管は「安定した収入」が確保できているのかを確認したいという意思表示になります。
在職証明書は、特に決まったフォーマットはないので、インターネット上で拾ったフォーマットをダウンロードしていただいて作成してもらうのでも大丈夫です。
会社が作成してくれた在職証明書に住所や勤務開始日が記載されている場合には注意
稀に、現住所ではない古い住所が記載されていたり、勤務開始日が「質問書」に記載した日付と違う場合があります。
古い住所の場合には面倒かもしれませんが、会社に行って修正してもらってください。
勤務開始日が違う場合は、会社に修正してもらえるのであれば修正してもらい、難しい場合は、なぜ「質問書」に記載した勤務開始日と違うのか別途理由書で説明するようにしてください。
文章で説明しないといけない場合
文章で説明を求められている場合は、要注意です。
例えば、「前婚の離婚原因の説明」「お付き合いから結婚に至るまでのより細かい詳細」を求められた場合には、結婚の信ぴょう性に疑義が生じているので、この説明はとても大切です。
説明の文章と一緒に証拠となる書類を一緒に提出するのが最も有効な方法ですが、結婚の信ぴょう性を証明するのは個々によって状況が変わるため一概になかなか「この書類が必要!」といえないのが難しいところです。
「プライベートなことだから」とオブラートに包んで説明するのではなく、情報が入管から外に漏れることはないので、嘘偽りなく正直に説明するのがポイントになります。
書類の提出期限と方法について
追加書類は、資料提出通知書に2週間~1カ月程度の期間で日付が記載されており、この期間内に準備して提出することになります。
追加書類の提出は、「郵送」でも「直接持っていく」のでもどちらでも大丈夫です。
直接持って行った方が審査に有利ということはないので、基本は郵送で追加提出することが多いです。
書類の提出期限に間に合わない場合の対処法
会社員などで仕事をしていると平日に書類を準備することが難しいので、2週間の期間はあっという間に過ぎてしまいます。
原則としては指定されている期間に追加書類を提出するのですが、書類の準備に時間がかかり、間に合わない場合もあると思います。
提出期限に間に合わない場合には、「入管に電話」または「直接」行って、提出期限を延ばしてもらえないか話をする必要があります。
東京入管や大阪入管の場合には、入管の電話がつながりづらいので、間に合わないと感じたら早めに電話をするようにしてください。
追加書類提出期限の当日にあわてて電話をしてつながらないと、最悪の場合、資料が提出されないということで審査に悪影響がでてしまうことがあります。
提出期限を延長してくれる場合は、どの程度延長可能なのか?
入管に交渉して延長してくれる目安は1週間~2週間になります。
ただし、むやみに長い期間延長してくれるわけではなく、「いつまでに準備できますか?」と聞かれます。
入管はなるべく早めに審査を終えたいので、1カ月延ばしたいと言っても、簡単には受け入れてもらえず、「なぜそんなに時間がかかるのか?」を聞かれます。
その理由を入管が納得してくれれば、1カ月の延長もあるかもしれませんが、基本的には1週間~2週間ほどになりますので、時間を見つけて準備するようにしてください。